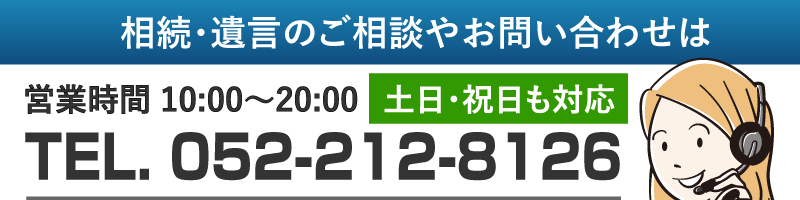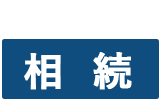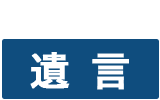相続についてのQ&A
相続についてのQ&A その100
相続についてのQ&A その99
父が亡くなり、相続人は母と私(子)と愛人の子となりますが、愛人の子については非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)ですが、法定相続分は通常よりも少なくなるのではないですか?
相続についてのQ&A その98
父が亡くなり、相続人は母と私(子1名)と思っていましたが、父に愛人がいたようで、その愛人の子が相続分を主張してきました。愛人の子であっても法定相続分は認められるのでしょうか?
相続についてのQ&A その97
相続についてのQ&A その96
相続についてのQ&A その95
相続についてのQ&A その94
相続についてのQ&A その93
相続についてのQ&A その92
相続についてのQ&A その91